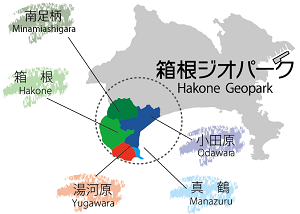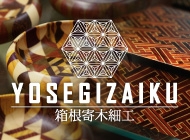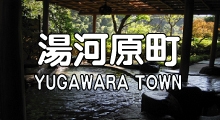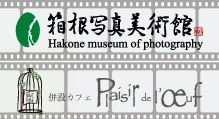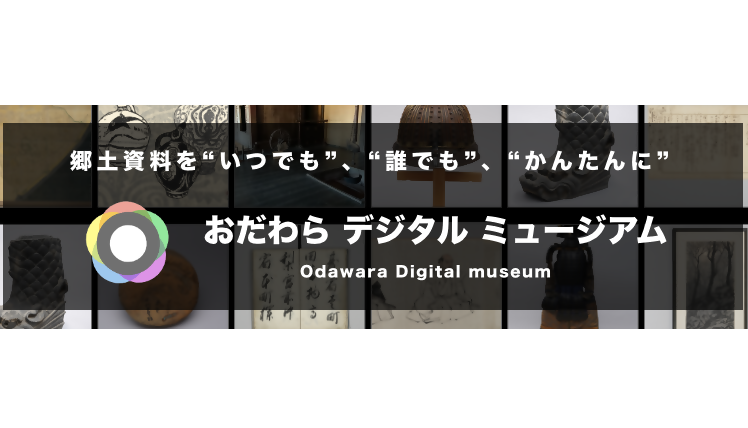南足柄市編入記念特設コーナー 南足柄ジオサイトフォトギャラリー

読み込み中.....
新たに認定されました南足柄市のジオサイトをご紹介します♪
Mi1 足柄峠と足柄道(矢倉沢往還)(あしがらとうげとあしがらどう(やぐらざわおうかん))
~万葉集にも詠まれる東西のみち~
| 足柄峠は、箱根峠よりも古くから重要な交通路であり、そこを通る足柄道は、奈良・平安時代より利用されていました。江戸時代、東海道が整備されると、矢倉沢往還として東海道の脇往還、大雄山最乗寺や伊勢原の大山、富士山への参詣道として利用されました。 |
【交通アクセス】
Mi2 矢倉岳(やぐらだけ)
~世界的にも貴重な深成岩体~
| 南足柄市の北側は、約200~100万年前に海底で積み重なった足柄層群が広がり、足柄山地を形成しています。約115 万年前にマグマが足柄層へ入り込んで冷え固まり、プレートの圧力により標高870mまで隆起しました。その後、周囲の足柄層が浸食され、石英閃緑岩(せきえいせんりょくがん)の岩体が現れました。矢倉岳は深成岩体が短期間で隆起した、世界的にも貴重な山なのです。 |
【交通アクセス】
Mi3 夕日の滝(ゆうひのたき)
~断層と侵食がつくった滝~
| 箱根外輪山を水源とする内川が、夕日の滝断層で落下して滝となっています。この断層は、箱根火山堆積物と足柄層との境にもなっており、軟質な足柄層群を浸食し落差20mの滝を形成しました。また、近くには金太郎の遊び石と言われる巨岩があり、この一帯が金太郎生誕の地という伝説が残っています。 |
【交通アクセス】
Mi4 蛤沢周辺(はまぐりざわしゅうへん)
~伊豆半島衝突の証拠~
| 当地域を含む伊豆半島は、かつては本州の南方にある火山島でした。これがフィリピン海プレートの運動により本州に近づき、200 万年ほど前から海底に土砂が積み重なり、足柄層群と呼ばれる地層が形成されました。70万年ほど前には本州と衝突し、さらに押され続けたために足柄層群は隆起し、足柄山地が生まれました。この地域は、古くからハマグリ等の化石が見られたことから、蛤沢と呼ばれています。 |
Mi5 文命堤(ぶんめいづつみ)
~氾濫と治水 双方に深く関わる火山活動~
| 関本丘陵(怒田丘陵)と呼ばれる本地域は、箱根火山による火砕流や内川や狩川から運ばれ積み重なった礫層(れきそう)によって形成されました。当丘陵地の北側は酒匂川に接しており、江戸時代に整備された文命堤上流の右岸では、箱根火山起源の火砕流堆積物が観察でき、この地域の災害と治水の歴史を知ることができます。 |
【交通アクセス】
Mi6 最乗寺と杉林(さいじょうじとすぎばやし)
~箱根外輪山の裾野に建ち多くの人が信仰~
| 箱根外輪山の裾野に建ち、600 年以上の歴史を持った曹洞宗では福井の永平寺、鶴見の総持寺に次ぐ古いお寺です。「どうりょうさん」と呼ばれて親しまれ、大勢の参詣者が訪れ、境内の荘厳なたたずまいが人々を惹き付ける、南足柄市を代表する観光地です。参道や境内には樹齢500年以上の杉の巨木が見られ、杉林は県の天然記念物に指定されています。 |
【交通アクセス】
Mi7 清左衛門地獄池(せいざえもんじごくいけ)
~豊かな水で南足柄発展に寄与~
| 箱根外輪山を水源として、1 日に1 万3 千t もの湧水量があります。この地を拓いた加藤清左衞門が水不足の折に水源を探していて馬もろとも吸い込まれ、その穴からこんこんと泉が湧き出したという伝説から、この名があります。この豊かな水資源を求めてフイルム工場が進出したことが、南足柄市の発展のきっかけとなりました。 |
【交通アクセス】
Mi8 御嶽神社と矢佐芝石丁場(みたけじんじゃとやさしばいしちょうば)
~箱根外輪山のふもとに建つ御嶽神社~
| 箱根外輪山の一つである明神ヶ岳のふもとにある三竹(みたけ)地区の鎮守神を祀る社(やしろ)です。平安時代に建立されたと伝えられ、正式には「御嶽権現神社」であり、三竹の地名はこの神社に由来すると言われています。この神社の石段には箱根火山起源の久野石が使われ、周辺の石丁場から切り出された石は、江戸城や小田原城の石垣に使われたと言われています。 |
【交通アクセス】
<
>